
【初心者必見】ホームページ公開後の運用について
CMSで簡単なホームページを作って運用してはみたものの、「何をしていいのか分からない!」という方に向けた、オススメの更新コンテンツをご紹介
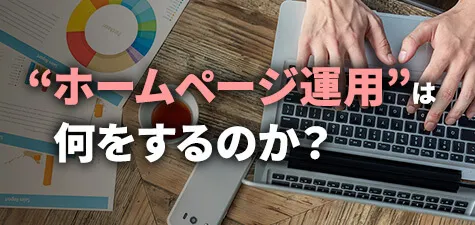
更新日:2025/3/28
ホームページで成果を出すためには、公開後の運用がなにより大切です。
しかし、ホームページの運用業務って一体なにをすればいいのかわからない、という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、ホームページ運用で必要な作業、その効果や外注時の注意点もあわせて解説します。
なお、ホームページ作成をご検討なら、Wepageをご検討ください。

ホームページの運用は、以下の点で重要です。
上記は事業を成功させるのに欠かせない要素ともいえるでしょう。
では、それぞれの重要性について詳しく解説します。

戦略的なホームページ運用は、結果として多くのユーザーが訪れるようになり、集客力や販売力の強化につながります。
Web上にコンテンツや情報を公開すれば、24時間いつでも宣伝できる広告として活用可能です。
また、自社商品・サービスに関する情報に興味を持ってくれるユーザーが多くなれば、自然と販売への誘導・成約率にもよい影響を与えるでしょう。
現代においては、オフラインのみで集客するよりも、オンラインも利用する方が集客・販売ともに効果は大きくなります。
ホームページ運用の継続は、顕在ニーズを持つユーザーだけでなく、潜在ニーズのユーザーも流入するので、新規顧客の開拓にも期待できます。
潜在ニーズだけでなく、さらに商品・サービス自体に興味がなかったユーザーにも届くようになれば、より幅広い顧客開拓ができるでしょう。
新規顧客の開拓ができれば、どのようなユーザー層にニーズがあるのかも再発見できます。
自社が想定していなかった顧客層からの支持が得られるなら、より市場規模の拡大に期待ができ、ビジネスチャンスを掴むこともできるでしょう。
自社商品・サービスを購入した顧客の満足度を向上させる上でも、ホームページの運用はメリットです。
例えば、新商品をどこよりも早く購入したいと考えている根強い顧客なら、ホームページから情報を得たいと考えます。
その際に、公式サイトが定期的に情報を更新していると安心を覚え、商品・サービスだけでなく、自社に愛着を抱いて応援してくれるようになるでしょう。
また、商品・サービスについて有益な知識・使い方などのコンテンツを発信していれば、より生活の質が上がるので満足度は向上するはずです。
このように、ホームページの運用の仕方によって、顧客満足度を向上させることができます。
定期的に情報が更新されているのが伝われば、企業やメディアとして信頼が得られる点もホームページ運用のメリットです。
もし、商品・サービスについて不明点を公式サイトから解決しようとした際、更新が3年前で途絶えていたらどのような印象を受けるでしょう。
おそらく、訪れたユーザーは企業・メディアとして大丈夫なのか、掲載している情報を信頼できるのか心配になるはずです。
逆に、常に情報が更新され続けていれば、今も活発的に事業に取り組んでいる印象を与えることができるでしょう。

ホームページは完成させたら終わりではなく、日常的かつ定期的に運用を行う必要があります。
そもそも良いホームページとは、常に情報が最新でありターゲットが好むデザイン・コンテンツであることです。
そのためには、コンセプトやイメージに合わせて更新・運用を行わなくてはいけません。
コンセプトやイメージが曖昧なままだと、運営方針もボヤけてしまい、ホームページ自体のクオリティが下がってしまうでしょう。
特にターゲットが何を求めているのかを常に考え、ホームページに落とし込んでいくべきです。
例えば、女性向けアパレルブランドのホームページを運用する際、どちらのホームページに魅力を感じるでしょうか。
おそらく前者ですよね。
このように、ターゲットを求めることを理解しつつ、日々のホームページ運用業務を遂行していきましょう。
では、具体的なホームページ運用業務について解説します。
ホームページの運用はコンテンツ更新業務がメインになるでしょう。
コンテンツは、
などがあります。
ホームページに訪れるユーザーに優先して発信したい項目は、情報をタイムラインで載せておける新着情報欄を設けるといいでしょう。
WordPressやJimdoのようなCMS(コンテンツマネジメントシステム)を利用している場合、コンテンツ更新業務は比較的楽に行えます。
一方、HTML・CSSなどのプログラミング言語を用いてホームページを構築している場合、直接言語を編集するため、ある程度の知識が必要です。
CMSを導入しておらず社内にエンジニアがいない場合には、制作会社に更新作業の依頼を検討しましょう。
また、CMSの更新できる範囲は種類によってさまざまです。
ホームページ制作を担当したエンジニアや制作会社にCMSの更新方法について聞いておくと後々スムーズに作業ができるでしょう。
ホームページに問い合わせフォームを設置していると、商品・サービスに関する質問だけでなく、クレームや取材申込、採用申込などさまざまな内容が届きます。
ホームページ運用担当の方は、上記を自分自身あるいは適切な部署へ確認する業務が必要です。
自分自身で回答できる分には問題ありませんが、部署へ確認をする際は手間や時間がかかり、業務の負担になります。
そのため、問い合わせの多い内容は、あらかじめマニュアルを作成しておきましょう。
マニュアルを作成しておけば、部署へ確認する手間が省け、なおかつユーザーを待たせる時間も少なくなり、クレームへと発展するのを防げます。
また、運用業務を引き継ぐ際にも問い合わせ対応に関するマニュアルは役立つはずです。
社内からもホームページに対して改善や要望などの依頼があるため、管理・報告をしなくてはいけません。
例えば、ショッピングカート機能に関するトラブル改善の依頼がきた場合は、エンジニアチームへ報告を行います。
管理・報告をする際は重要度・優先度をもとに振り分けていくといいでしょう。
ショッピングカート機能が使えない場合、ユーザーが購入できないため重要度・優先度ともに高いため、早急に報告を行うといった流れです。

ホームページを公開するには、ドメインとサーバーが必要です。
サーバーを自社で用意しているところもありますが、ほとんどの企業がレンタルサーバーを契約しているはずです。
ドメインとサーバーの契約は、更新作業を忘れないようにしなくてはいけません。
更新作業を忘れるとホームページの公開ができなくなります。
そのため、ホームページの運用担当者が、
上記を管理しておきましょう。
実際のドメイン・サーバーの設定や更新作業は社内のエンジニアや制作会社に任せておけば問題ありません。
もし、現状でドメイン・サーバーの詳細がわからない場合は、ホームページ制作担当者や制作会社に聞いておきましょう。
ホームページを運用していく中で、想定外のトラブルが起こる可能性はゼロではありません。
特にホームページが閲覧できない状態は緊急性が高く、早急に対処すべきトラブルの1つです。
もしトラブルが発生した際に、どのような対応をするのか決めておくのも運用担当として重要でしょう。
例えば、トラブル発生時に以下のようなフローで対応ができます。
| 1. | トラブル発生の連絡 |
| 2. | 運用担当者がトラブルの確認 |
| 3. | 運用担当者がエンジニアあるいは制作会社へトラブル修正の依頼 |
| 4. | 社内・ユーザーに対してトラブル内容の伝達 |
| 5. | 解決次第、社内周知+ホームページ上でお詫びを掲載 |
トラブル内容によって変わりますが、メルマガや会員限定メールの配信を行っている場合は、ユーザーにも連絡した方が親切です。
トラブル時のフローを決めておき、冷静かつすぐに対処できるように心がけておきましょう。


ホームページを運用する際に重要なのは、ユーザーから見えない部分をサポートするバックエンド業務です。
バックエンド業務は主にサーバーやデータベースの保守・管理やシステム開発を指します。
ホームページ運用においては、サーバーに関する対応が該当するでしょう。
バックエンド業務を疎かにしていると、ホームページがエラーによって表示できなくなるケースもあります。
訪れるユーザーに安心して閲覧・利用してもらうためにも、バックエンド業務でどのようなことを行うのか知っておきましょう。
多くの企業が運営しているホームページは、独自ドメインとレンタルサーバーを契約しています。
独自ドメインとレンタルサーバーは有効期限があるので、ホームページの運用をするなら定期的な更新が必要です。
もしドメイン・サーバーいずれかの有効期限が切れてしまうと、ホームページが表示できなくなってしまいます。
運用を続けるにあたって絶対に避けるべきなので、必ずドメイン・サーバーの管理は怠らないようにしましょう。
また、ドメインの認証やホームページ運営企業が実在することを証明するのがSSLサーバー証明書です。
SSLサーバー証明書が適用されていると、URL冒頭部分が「http」から「https」に変わります。
現在では、URLがSSL化されていた方が掲載順位を引き上げることをGoogleが発表しています。
そのため、ドメイン・サーバーと同様に、SSLサーバー証明書の更新も忘れないように管理しましょう。
CMS(コンテンツマネジメントシステム)は、プログラミング知識がなくても簡単にホームページが作成できるシステムです。
その中でも「WordPress(ワードプレス)」は有名なCMSのひとつで、更新のしやすさやカスタマイズのしやすさから、導入している企業も少なくありません。
このWordPressを用いたホームページの場合、セキュリティの観点からアップデートを定期的に行う必要があります。
また、中には使用しているプラグインのアップデートもあるので、バックエンド業務で対応しなくてはいけません。
CMSによっては、こういったアップデート業務を提供側が常に行ってくれるサービスもあります。
バックエンドにおいて欠かせない業務がデータのバックアップです。
なんらかのエラーによって、作業中やこれまでのデータが削除されてしまった場合、バックアップがあれば復元ができます。
エラーはいつ何時起こるかわからないため、定期的なバックアップを行い、万が一のときに備えておかなくてはいけません。
データのバックアップ作業自体は難しくはありませんが、定期的に行わなければならない点においては、手間に感じる場合も多いでしょう。
ホームページを運用していると、トラブルが発生するケースも珍しくありません。
トラブルによってホームページが表示できないと、ユーザーが商品・サービスを購入できず、自社にとって機会損失になるでしょう。
また、表示されないことによってユーザーの不満も溜まるので、トラブルが起こったらすぐに対処すべきです。
上記の流れでトラブル対応を行いましょう。

ここでは、ホームページのアクセス数・問い合わせを増やすための運用ヒントについてご紹介します。
上記2点を取り入れて、効率よく成果を出していきましょう。

アクセス数や問い合わせを増やすためには、訪れるユーザーの動向や属性を解析するのが大切です。
解析するにあたってGoogleが提供する無料解析ツール「Google アナリティクス」と「Google Search Console」をおすすめします。
Googleアナリティクスは、ホームページに訪れたユーザーの動向や自社が設定したゴールに対し、どのくらいのCVR(コンバージョンレート=購入や申込にどれくらい至っているかその割合)だったのか把握可能です。
例えば、
以上の項目がGoogleアナリティクスで解析できます。
Google Search Consoleに関しては、ホームページに至るまでの経路や検索ワード、Googleへ新規ページや更新ページの申請を行うツールです。
自社サイトにどのようなワードで検索してたどり着いたのかがわかれば、ユーザーのニーズも見えてきます。
また、SNSや検索エンジン、広告からの流入数を比較して、どの媒体に予算を費やせばいいのかも分析可能です。
上記の解析ツールを用いて、ホームページの課題や改善点を発見するのも大切な運用といえます。
有料の解析ツールを使えば便利な機能やより分析がしやすくなりますが、まずはGoogleが提供する無料でも使えるツールを使って運用してみましょう。
ホームページを存続させるためには集客をしなくてはいけません。
ホームページの運用担当者は集客作業もメインの業務として考えていきましょう。
Web上での集客方法には無料・有料の2種類があり、どちらもやり方によって効果的な手法となります。
では、それぞれどのような方法があるのでしょうか。
ホームページに無料で集客するには、以下の4つの方法があります。
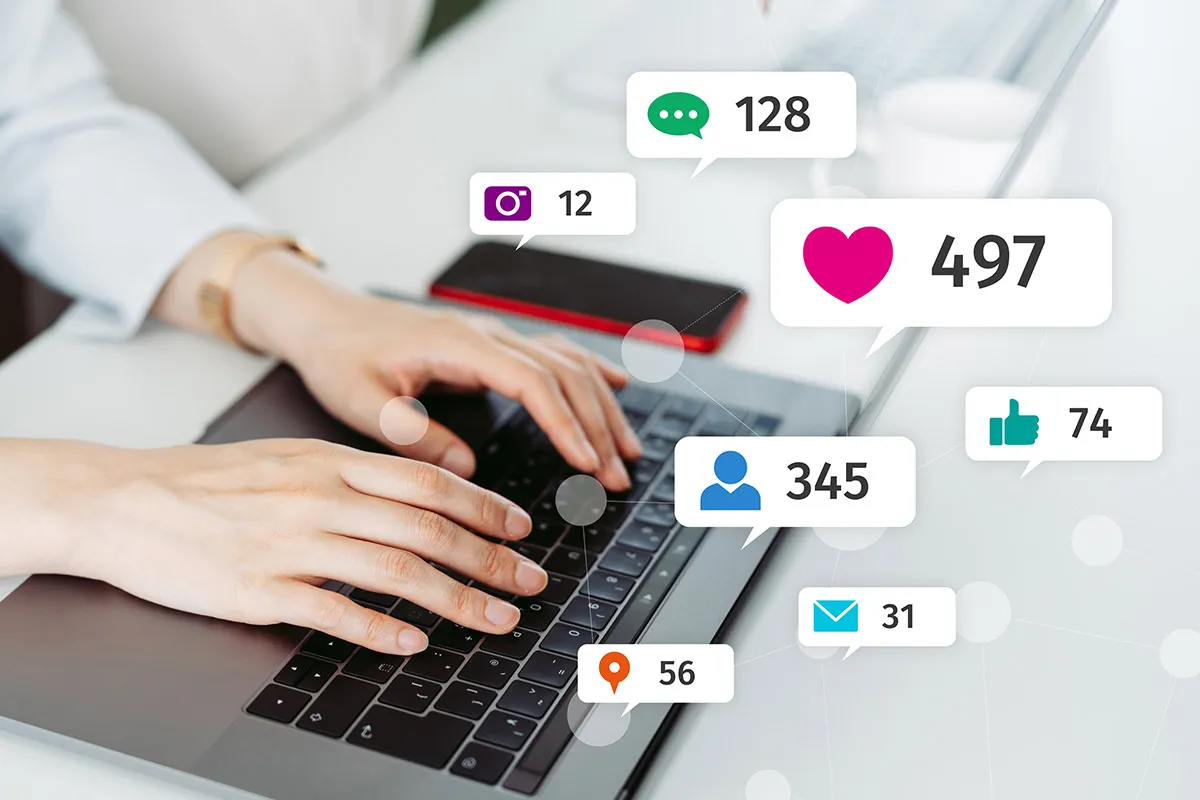
どれも無料で行えるものばかりですが長期的な施策が多く、すぐに成果を求めるものではありません。
しかし、上記の集客法が成功すれば、顧客やファンが安定的に増やせるため、有料で集客する方法と並行して行うのがおすすめです。

有料で集客する代表的な方法は広告を利用することです。
現在ではさまざまな広告が溢れており、コストを割く以上はどの広告を利用するのかを考えなくてはいけません。
まずは、ホームページの認知度を高めたいのか、商品・サービスを購入してもらいたいのかを決めてください。
その上で、自社のターゲットとなるユーザーがどの広告を目にする機会が多いのかを調査しましょう。
利用できる広告は多く、
以上のような種類があります。
広告は成果を見ながらPDCAを回しやすいので、予算が確保できているなら積極的に運用しましょう。

ホームページ運用で重要なポイントは、主に以下の4つです。
それぞれのポイントを理解するために、しっかりと読み進めていきましょう。

ホームページはただ運用していても、集客力や販売力は強化されません。
意識すべきはコンテンツが検索上位に表示されるようにSEO対策をすることです。
近年のSEOは特に専門性や権威性、信頼性を重視しているため、ユーザーのためになるコンテンツが評価されやすくなっています。
まずは、コンテンツごとにキーワードを決めて、付随する顕在的・潜在的な悩みを解消できるよう構成を考えましょう。
慣れないうちはキーワード選定も難しいため、コンテンツ制作のみ外注するという方法も視野に入れておくといいかもしれません。
TwitterやインスタグラムなどのSNSアカウントを持っているなら、並行して運用するのも検討すべきです。
現代のマーケティングにおいてSNSはなくてはならない存在であり、活用次第では効率よくホームページへ誘導できます。
また、ホームページとSNSで同じテーマでも異なる内容の情報発信を行えば、興味のあるユーザーをより惹きつけることもできるでしょう。
業務の負担は大きくなるものの、効率や効果を考えると、SNSの運用も並行して行うのがおすすめです。
ホームページ運用を専門とするチームがあれば問題ありませんが、多くは他業務と兼任しているため、優先度が低くなるケースも珍しくありません。
そうなると、ホームページの目的達成から遠くなってしまうので、役割分担ができるよう担当者・チームを構築しておきましょう。
これまで解説した業務を考えると、Web担当を1人に任せるのは負担が大きすぎます。
そのため、効率よくホームページ運用業務を割り振っていき、1人1人の負担が軽くなるよう調整しましょう。

ホームページを成長させる、良質なコンテンツを生み出していく場合には、会社全体での協力が必要不可欠です。
会社全体の協力を得るためには、円滑に情報を共有できる体制を整えなくてはいけません。
例えば、社内で使用しているグループウェアや社内SNSに、運用に関する事項を周知するなどです。
また、現場の方にしかわからない専門的な話も、コミュニケーションを取ることでコンテンツ化へと実現できます。
情報共有の方法を整備したら、社内全体でのコミュニケーションを積極的に行い、会社でホームページを作り上げていく意識を持たせましょう。

運用業務を自社で補いきれない場合は、外部委託を検討するでしょう。
しかし、外部委託する際は以下の点に注意しなくてはいけません。
これから注意点について解説しますので、適切な外部委託ができるようになりましょう。
外注する際の相場は、運用内容をどこまで依頼するのかで変わります。
運用担当者自身ができる作業以外の部分をカバーする形で外注すると、必要以上にコストをかけず、なおかつ効率よく運用ができるでしょう。
大まかな相場については以下の通りです。
運用担当者がどこまで技術を持っているのか、集客に困っているのか、何に困っているのかなどもよく吟味しながら、運用業務の外注を検討しましょう。
運用業務を外注する場合は、業務内容・対応頻度・費用を明記しておく必要があります。
| 外注項目 | 抑えるポイント |
| 業務内容 |
専門知識が必要、あるいは時間がかかる作業は外注を要検討 会社によっては月次レポートや改善施策の提案も可能 |
| 対応頻度 |
月に何回、何時間の作業をしてもらいたいのかを記載 会社によってコンサルもしてもらえるので、必要の有無も検討 |
| 費用 |
予算がどのくらい確保できるのか記載 会社によって月額・発生作業ベースなど費用形態が異なる |
自社で上記の項目をある程度決めておけば、外注先に見積もりを依頼したとしても要件が把握しやすく外注先がプランを提案しやすくなります。
外注先に全て丸投げするのではなく、自社が必要としている部分をしっかりと明確にして交渉しましょう。

簡単にホームページ作成および運用を行いたいという方は、弊社が提供している「Wepage(ウィーページ)」をおすすめします。
Wepage(ウィーページ)では、誰でも簡単に操作ができるホームページ作成ツールです。
難しいスキルや操作が不要なため、日々の運用業務の効率化ができ、なおかつ属人化を防ぐことができます。
Wepage(ウィーページ)は利用料無料のフリープランをご用意しておりますので、まずはお気軽にお試しください。
今回は、ホームページを運用するにあたって作業の内容やポイント、外部業者委託の注意点について解説しました。
ホームページを運用するには、コンセプトや方針の決定、ターゲットに沿ったデザイン・コンテンツが重要です。
また、ドメイン・サーバーの保守管理やトラブル対応などのバックエンド業務も日々こなしていく必要があります。
ホームページで求める成果を得るには、長期的な視野をもって施策を行わなくてはいけません。
そのため、自社で内製化ができるか、外部委託をすべきかを見極めつつ、適切かつ効率のよい方法で運用業務にあたりましょう。
ぜひ、顧客が魅力に感じるホームページに仕上げてください。